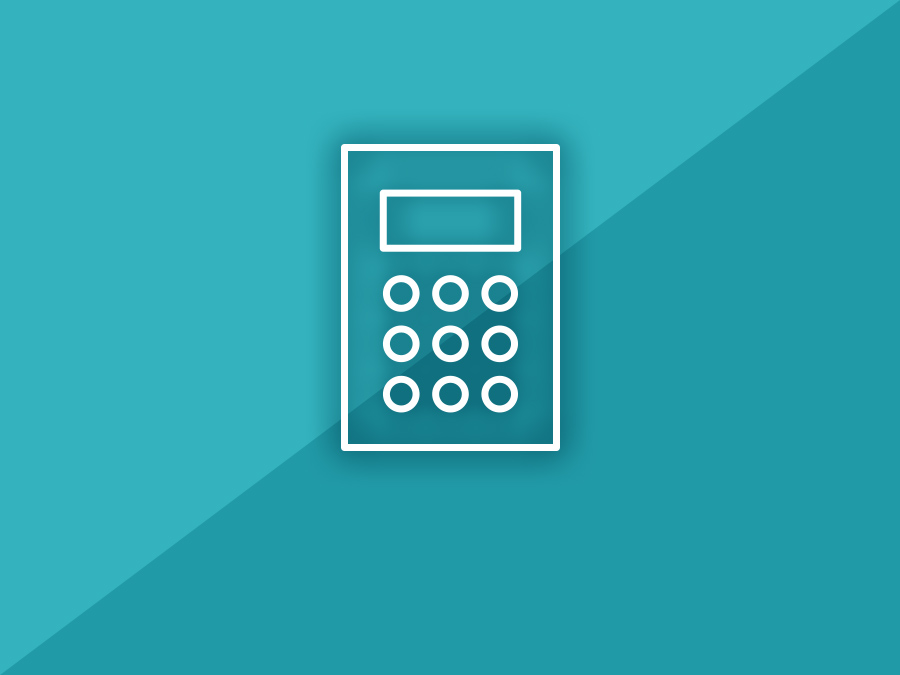特定技能制度
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていくものです。

最新資料はこちら(出入国在留管理庁HP)をご覧ください。
「特定技能制度」に関するご相談は、ITE事業協同組合にお問い合わせください。
営業日︰月~金曜日 第1・3土曜日
営業時間︰10:00~17:00

特定技能制度のメリット
国際貢献を制度の目的とした技能実習制度と違い、日本企業の人手不足を補うことを目的として制定されていますので働き手不足の解消に直接的に繋がります。
「人手不足を補うため」の制度なので、受入れ人数には制限がありません。
※建設分野、介護分野は例外となります。
特定技能制度は、特定技能評価試験と日本語評価試験への合格を特定技能取得の条件としています。
そのため、一定の知識や技能を持った状態の方を雇用することができます。
許可や申請などの関係で約半年の期間を必要とする技能実習生と違い、特定技能制度での入国の場合は試験に合格していれば即戦力としての雇用が可能です。
通常、外国人をアルバイトで採用すると週28時間以内でしか雇用できませんが、特定技能の場合はフルタイムでの雇用が可能です。
特定技能制度のデメリット
技能実習制度とは違い、特定技能の場合は転職が可能です。
そのため、労働条件や就労環境次第で転職されてしまうかもしれないという点を企業側は留意しておかなければなりません。
特定技能を取得する外国人労働者に、最低賃金で働いてもらうことは法律上できません。
特定技能を取得している外国人を雇う場合、毎月の給料に加えて、登録支援機関への支援費を払う必要があります。
特定技能制度は施行されてから比較的日が浅い制度であり、社会情勢なども含めて受入れ態勢の遅れが指摘されています。また、海外での試験が限定されているので、技能実習と比べても候補者の確保が難しいのが現実です。
在留資格「特定技能」の2号であれば、在留期間がなく就労することが可能ですが、特定技能1号の場合は最長でも通算5年の雇用期間を定められています。(特定技能2号への移行対象外の業種に限ります。)
特定技能制度を利用して就労する外国人労働者の「支援」を目的とした登録支援機関は、条件を満たしていれば、民間団体や個人事業主でも新規参入することができます。
そのため、企業側はより慎重にパートナーを探す必要があります。